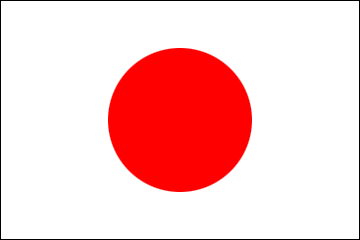大使館関係者の声:小松勇輝草の根外部委嘱員
令和5年5月8日


草の根外部委嘱員としての契約業務を終えて
2023年3月27日
小松勇輝
草の根・人間の安全保障無償資金協力外部委嘱員(以下:草の根外部委嘱員)としての契約業務を終えるにあたり、約2年2ヵ月間の活動を振り返り、ご挨拶とさせていただきます。なお、本稿の内容はすべて個人の主観に基づくものです。
本稿では、はじめに当館における草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下:草の根無償)を概観し、次に約2年間の活動を筆者の主観的な要点ごとに振り返ります。
【在コートジボワール日本国大使館における草の根無償】
草の根無償は、非政府組織や地方公共団体を対象とした、対象地域の住民に直接裨益する小規模な事業のための原則1,000万円以下の無償資金協力です。当館は、コートジボワール共和国に加え、トーゴ共和国及びニジェール共和国を兼轄し、校舎建設などの教育分野と地方保健センター整備などの保健分野を中心に新規案件を形成しています。実際に私は、契約業務期間中に3カ国合計で13件の新規案件形成に関わらせていただきました。また、新規案件に加え、これまでに実施された案件の管理も並行して行いました。
上述のように当館では、教育や保健分野の案件が中心ですが、分野と一括りにしても国や地域ごとの文化や制度の違いから、案件ごとのニーズの詳細な違いまで、同じように形成できる案件は1つとしてありません。その中で、現地に足を運び、対話を重ね、その地域の人々が直面する課題を解決するための一助となるよう、様々な調整をすることが草の根外部委嘱員の役割です。
【現地を想像し、現地の人々と創造する】
前述した通り、草の根無償の案件形成では、現地に足を運ぶことが業務上、非常に大切です。しかしそれだけではなく、現地で把握したものをどのように伝えるかが更に重要となります。すなわち、現地に実際に行ったことのない方々がどれだけ鮮明に現地の状況を想像し把握できるかということです。現地の状況をその案件に関わる全ての人が同じ解像度で共有できるよう努力することが重要であり、それが案件形成の鍵となります。
また、案件の形成は供与側と被供与側どちらか一方の主導で進められるものではありません。無論、両者の事情や思いが交差することは往々にしてあります。しかし、草の根外部委嘱員が現地の人々と供与者の架け橋となり、被供与側と供与側が協働して案件を創造することで、より効果の発現性の高い案件を形成することができると感じました。
【たしかなインパクトとジレンマ】
私は草の根外部委嘱員として当館で従事する以前にJICA海外協力隊(以下:協力隊)として2年間、当地と同じ仏語圏西アフリカのベナン共和国で活動していました。協力隊は、政府開発援助において開発途上国からの要請に基づき、それに見合った技術・知識・経験を開発途上国の人々のために生かすものであるため、草の根無償のような学校建設などのハード面の支援は基本的に実施することができません。翻って、上記のように草の根無償ではハード面の支援が中心のため、技術協力等のソフト面の支援は基本的に対象外です。このように、2つの異なる性質を内包した援助スキームにそれぞれ2年間携わってきた中で、一番に感じたことは、たしかなインパクトと限界でした。例えば、協力隊では藁葺きの簡易教室で地面に座って授業を受けているという現実に何もできなかったり、草の根無償では供与機材の維持管理の困難に直面したり、自分の無力さを思い知らされる場面が多くありました。しかし当館での活動を通して、それぞれの2年間でジレンマに感じ、なすすべのなかった部分に対して、たしかなインパクトを残すことができたと実感することができました。
その反面、各スキームにおける限界を理解しながらも、人々が直面する課題に対する包括的な解決には至らなかったと感じる場面が多かったことも事実です。これまでの様々な経験を通して、自身の2つの異なる経験は相互補完され俯瞰することができましたが、対象地域や時間軸が異なるため、各課題に対するインパクトの相互補完ができたわけではありませんでした。そのため、これら経験は自分の中だけで昇華するものではなく、今後のどのような形であっても社会に還元し、諸課題に対して包括的なインパクトを残すことができるよう努力していくことが求められていると強く感じました。
【最後に】
近年、変化の目まぐるしい世界情勢の中で、様々な事象が多様化しています。その中で世界中の人々が同じ方向を向き、すべての人々が何不自由なく暮らせる世界は、少なくとも私の生涯では実現されることはないかもしれません。しかし、私が関わらせていただいた草の根無償という、政府開発援助の中では相対的には小さなアクションがその実現の一助となっていることを切に願います。そして最後に、この2年間で関わらせていただいたすべての方々にこの場を拝借して感謝申し上げます。